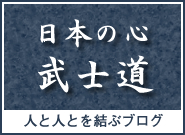逆境の意味
2010年5月21日
日記
今年に入ってから、肺炎になり、3月に母を身罷り、5月に父が骨折と色々と教えの多い年です。
何かがあるごとに学ぶことがあり、逆境が設定されている意味や意義が良く解るようになりました。
もちろん反省ではなく後悔してしまうこともあります。
でも、後悔しても何も得ることがなく、心が空しく苦しくなるだけということもわかりました。
今は忙しいからこそ、自宅から片道2時間半の父のところへ週に1~2回、仕事やボランティアの合間をぬって必ず行くようにしています。
私が父のところへ行くと必ず歓待してくれます。
週に一回行き続けて、私をこんなに歓待してくれる人が他にいるかな・・・って考えたら、有り難いな。。。
親は居て、見てくれて当たり前だったけど、改めて考えてみると、すごいことだったって事がわかります。
親孝行できることは、幸せなことなんですね。
明日は、京都。
武士道人間力向上セミナーです。
また会員の皆さんとお会いできると思うと、とても楽しく嬉しくなります。
2010年5月21日 11:08 PM | 日記 |
食べ物
武士道ワンポイントレッスン
四回目のテーマは「食べ物」
地球に人類しか存在しなかったらどうなるの?
こんな事を考えたことはありますか?
地球上に人類しか存在しなかったら、間違いなく人間は共食いをするしかありません。
それこそ弱肉強食です。
弱い者はいつも恐怖に怯えて、命からがら逃げ惑うしかありません。
我々の食べ物は何なのか? 考えたことはありますか?
食べ物は全て生きとし生けるものの命です。
生ある他の生き物の尊い命を食べ物として頂戴し、人間も動物も魚も生きているのです。
自然に従って生きている動物たちは貯蔵をしません。
アフリカの炎天下に住んでいても、冷蔵庫も冷凍庫も持ち合わせません。
だから、たった今、その場で必要な分だけの命を頂きます。
残った物は、ハイエナや他の生き物に上げて、捨てはしません。
てんとう虫とアブラムシの関係だって、てんとう虫はアブラムシを苦しませずに殺し、その後はみんなで仲良く分け合って食べて、何一つとして無駄を出しません。
人間は自然に逆らって生きています。
だから、自己の安全と安心の為に貯蔵をします。
そして、余分だと思うと、生き物を殺している事を忘れて、平気で捨て去ります。
これは、他の生き物の命を軽視しているということです。
だから、自分の命も粗末に扱って、自殺をするのです。
自殺をするのは人間だけでしょう。
犬や猫が自殺したなんて聞いたことがありません。
そして、人間を天敵とする生き物がいません。
人間は走るのも、噛み付くのも、引っかくのも、泳ぐのも、飛ぶのも、それぞれの動物と比べてみても秀でているものがない、肉体的には弱い生き物だからです。
その弱い生き物が生きていけるように、智恵を授かっています。
だから、その智恵は自然界を融和させて調和を図るために使うことが、与えられたものの使命であると思います。
しかし、現代の人間は智恵を自分たちのためだけに使っています。
自然界で天敵に狙われるた生き物は、安楽死ができる自然の仕組みがあります。
蛇ににらまれた蛙は気絶してしまい、飲み込まれたときは苦しくありません。
鷹に襲われた狐は、急所を爪でつかれるから痛みも苦しみもなく即死できます。
ライオンに襲われたシマウマが、飛びつかれてから苦しい顔をして逃げ惑うことはなく、飛びつかれたと同時に気絶してしまいます。
でも、人間の食べ物となる牛も豚も鶏も、殺されるときは悲鳴を上げて嫌がり苦しみます。
それなのに、人間はその肉を平気で捨てています。
人間はもっと自然と融和する事を考えて、自然の摂理に則った謙虚な生き方をすべき時がきているのではないでしょうか?
生きとし生けるものの命を大切にすることが、結果的に自分の命も大切にするということになり、自殺撲滅につながると思えませんか?
自殺をする人は、産んでくださったお母様に感謝をするのをわすれていると思います。
生みの苦しみ、育てる大変さ、税金を使って学問を身につけ、多くの人の親切で大人になります。
母親に感謝がないから、人間には命を投げ出してくれている生き物に対しても感謝がありません。
感謝があればむげに捨てたりはしなくなります。
でも、魚が切り身でテーブルに出ていると、命あるものだったという意識がまったく起きないのも確かです。
ましてやミンチされて、お団子にでもなっていたら、小さい子供の誰が、元が海老だったとか、鶏だったとか・・・想像つくでしょうか?
嫌なことがあると、生命の大切さが解らないから命を捨てることを考えてしまうでしょう。
命の大切さは親が教えたり学校で教えなければ、気が付かないまま大人になってしまいます。
微分積分や難しい方程式は解けるのに、命の大切さに気が付かない大人になってしまうのです。
生命とは何なのか?
もう一度考える必要があると思います。
そして、生命とは何か?
ここを意識をすることで、物を大切にしたり、親孝行をしたり、生き物を大切にする、無駄をしない、などという考えが育つのではないでしょうか。
日本の宗教である神道というものは、自然を讃え、自然を敬い、自然と融和するための方法だったと思います。
雷を畏怖し、雨を畏怖し、お天道様に感謝して、自然と共に生きてきました。
でも戦後は高度成長のもと、宗教に対する間違った認識を植え込まれ、感謝を忘れて命を粗末に生きてきたように思えます。
そこへおかしな新興宗教が犯罪をおかしたから、たまったものではありません。
故に、自殺者が年間3万人を超えてしまうという、残念な結果が今あるように思います。
自殺者をなくすために、相談所を作るのと同時に、もう一度、生命について考えて、自然の中で生きている事を思い出すことからはじめてはいかがでしょう。
武士道はこういうところにも生きています。
By 本多百代・人間力向上セミナーより
2010年5月21日 07:15 PM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |
今日は、長久手古戦場跡の近くで社員研修
2010年5月20日
5月20日 日記
私は武士道というテーマと通して、子供の育成、育児支援、人間力の向上、社員育成、食の道、などに力を注いでいます。
仕事としているもの、ボランティア活動でしているものとありますが、結果的に日本人の力を底上げすることに一生懸命努力しています。
とっても忙しいから、本当に悩む暇もなくて、逆境が来ているのに逆境を片付けることしか頭にないうちに、逆境を乗り越えていたりします。
確かに逆境って初めは大きくてなかなか乗り越えられないのだけど、一度乗り越えると次からは気が付いたら逆境山の頂上にいたりするんです。
これも癖で、逆境乗り越えグセをつければ、あまり悩まずスラッと乗り越えられるようになるから不思議ですね。
さてさて今日は、長久手古戦場跡の近くで、社員研修でリーダー研修とアテンダント研修をしてきました。
内容はリーダー研修では、建仁寺の俊崖和尚と釈宗演という小坊主の話から、和尚のように失敗した小坊主に対しても、人としての尊厳を守った対応をすることについて掘り下げました。
アテンダント研修では責任について話し、全員が責任について理解して、具体的に行動に移せるようにしました。
ついつい脱線して、テキストにない話をしてしまうのですが、鹿島さんが「その線でずっと話してください」といってくれたから、その気になってしまい、押さえるところを押さえながらも、楽しい3時間を過ごしてきました。
親孝行な鹿島さん、日々の愉快なやり取りをご披露してくださいな(笑)
それに今日私が受けたのは、「謝っても許したくない」と言われたら?という質問に、川崎さんの「じゃあどうすればいいんですか?と聞いちゃう」でした。
それに対して、「そんなことを言ったら余計に激怒されるわよ」と言われた時の川崎さんの困った顔が可愛かったです。
印象に残ったのは研修中の宮尾さんの足が綺麗だったこと。宮尾さんは足だけでなく顔も綺麗なんですけどね。
そして、最近メキメキカリスマ性を発揮してきた浅井さん(普段はこんなに気取った呼び方をしてないのですが)、応援しているから今日の逆境を乗り越えてくださいね。
発言のなかった人は次回に登場してもらいます。
みんなの明日の成長が楽しみです。
2010年5月20日 11:57 PM | 日記 |
「ゆとり」
武士道ワンポイントレッスン
三回目のテーマは「ゆとり」
ゆとり教育が失敗だったことは周知の如く。
でも、良く聞く言葉ですが、「ゆとりを持って仕事をしたい」とか「ゆとりが欲しい」と言う人が多くいらっしゃいます。
それでは、ゆとりってなあに?
―――余分に時間を取っておくこではないでしょうか?
それって時間の無駄遣いではありませんか?
―――うう~ん・・・それじゃ・・・少し多く予備を取っておき、失敗しても良いようにすること?
それって資源の無駄とは思いませんか?
―――私、難しいことはあまりよくわからないのですが!!!ブチ (ああ・・・切れちゃった)
このように「ゆとり」って言葉を曖昧にしか理解していないのに、あたかも解っているような錯覚で使っているように感じますね。
それでは
武士道 “ゆとり” の定義
「誰よりも一生懸命努力して、工夫して、危機管理もして、シャカリキに頑張った結果、前より速くできるようになったり、前より緊張しないでできるようになることで、時間や気持ちに余裕が生まれる事」
つまり、努力の結果に生まれた時間や気持ちの余裕を指すのであって、無駄に時間を確保しておくことではありません。
この無駄に時間を確保したことから、怠けたり、緊張感がなくなり失敗をしたりすることが多くなり、ますます自信をなくす結果を導いてしまいました。
よって、ゆとり教育が失敗したのは、ゆとりを楽をすること、辛い努力はなくすことという方向に解釈したからといえます。
遊ぶ時間を余分に取って楽をさせたのでは、学力が低下します。
それは、知識の欠乏を意味しますから、判断力が低下し、犯罪が増加、意欲は低下、よって自己中になってしまうわけです。
正しい“ゆとり教育”をするなら、
・少数精鋭授業にする
・子供達のわからないところを放課後たや日祭日も補講授業をして解るまで教える
・それらの補講の為に、補講専任講師を正規で採用する(補講専任講師の出勤時間をずらして午後13時~21時にするなど工夫する)
・現代はクーラーもヒーターも空調設備が整っているのだから、学力が追いつかない子は夏休みを減らして2週間くらいにして、他の日には補講を入れる
・春休みも、正規の教諭は補講に携わらなくて良いのだから、先生は新学年の準備に集中でき、子供は補講を受けることで取りこぼしがなくなる。
この様にすれば、雇用促進という社会貢献をしつつ、子供達はIQも学力も上がり、勉強をする気持ちにゆとりが生じる一石二鳥の優れた結果を得られることでしょう。
偏差値をなくして、学力テストを廃止しても、子供達の心にゆとりは生まれませんでした。
ゆとりは心に生まれなければ意味がありません。
時間のゆとりとは、言い換えれば暇なんですから。
それこそ暇をもてあましているから、細かいことに気がいき、人のことが気になっておせっかいになったり、過干渉になったり、それがイジメにだって発展するのですから。
忙しければ悩む暇だってありません。
時間ではなく心にゆとりを持つには、自信が付かなければなりません。
努力の末に勝ち取った自信から「ゆとり」は生まれるのです。
ゆとりとは、極めることにより湧き出る自信の産物であり、自信に伴うその人の風格に値するともいえます。
だから、失敗もなくなるから、ますますゆとりが生まれ、逆境にも挑む心の強さや勇気が育つのです。
ゆとりを得るには、必死になって努力することが条件であることを忘れてはなりません。
By 本多百代・人間力向上セミナーより
2010年5月20日 11:29 PM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |
名古屋育児セミナー
2010年5月19日

5月19日
今日は名古屋で育児支援セミナーと題して、武士道を育児に活かしたセミナーを開きました。
山口達也社長が名づけて「チビまま子ちゃん」で、毎月1回定期開催しています。
名古屋市緑区の(有)キャンプスのセミナールームで開催しています。
本日は、トイレの神様の歌から、トイレには拝み上手な神様がいらっしゃるから、綺麗にしておくと一緒に拝んでくださるらしい・・・とか、トイレの神様は女神様らしい・・・、お腹に赤ちゃんがいる時に一生懸命トイレ掃除をすると、綺麗な顔をした子供が生まれるらしいなどと話が出ました。
私はまだこの歌を聞いたことがないのですが、今年の年末には千の風に乗ってなみに流行するみたいですね。
そこで、内容も鍵山秀三郎武士道協会理事(イエローハット相談役、日本を美しくする会相談役)に学び、掃除道から勉強をしました。
トイレ掃除の奥深さを感じたという感想が多かったように思います。
悩みをかかえたり、心細かったりする若いお母様たちが、にこやかになって帰る姿が励みになっています。
名古屋市緑区で毎月1回開催しております。
興味のある方、一人で育児に悩んでいる方、是非ご連絡下さい。
ブログに匿名でもいいので「名古屋育児セミナー参加希望」と書いてくだされば、連絡先をお知らせします。
だれでも参加できます。
昨日、昨日池上さんに作って頂いたお寿司は、五目寿司だそうです。チラシ寿司ではないそうです。
五目寿司はご飯の中に具が混ぜ合わせてあり、チラシ寿司はご飯の上に具を散らしてあるのだそうです。
確かに、混ぜ合わせてありました。本当に美味しかったです。
2010年5月19日 11:18 PM | 日記 |
武士道子供学校を開きたい!
2010年5月18日
5月18日の日記
週末の人間力向上セミナーin京都の内容を思案中。
祝詞、論語、お経を学んだものを現代に生かすことでまとめようと思っているんです。
今日は名古屋。池上さんがチラシ寿司を作ってくださいました。
母の味で本当に美味しかった。一人で頂く夕飯も淋しく感じませんでした。
それに、手作りパンも焼いてくださって、至れり尽くせりの優しい池上さんは元小学校の先生で、私が名古屋で育児セミナーを開く時に一緒に講師をして手伝って下さっているんです。
名古屋でも武士道子供教室を開きたいという話が出ています。
道徳教育(修身学)が学校教育から消えてしまってから60数年がたち、今また子供を持つ母親から道徳教育をして欲しいという依頼が入ってきます。
安倍元首相が徳育教育に取り組んだとたんにマスコミに叩かれてしまいましたが、今思い返すと本当に必要な事を始めようとして勇気のある素晴らしい人が安倍さんだったように思うんですけどぉ~。
皆さんどう思われますか?
2010年5月18日 11:09 PM | 日記 |
使う言葉の工夫
武士道精神 その2
武士道精神を声高に説法して他者に求める人がいます。
でもそういう方に限って、ご自身は「え?!」という行動をします。
なぜなんでしょうね・・・
それは「武士道とはこうあるべき」という固定概念があり、それから外れることを許さない、或いは、許せないという一本気なところがあり、強いのでしょう。
しかし、武士道は簡単言うと「配慮」であるから、決め付けたりすることはできないはずです。
決め付けたらマニュアルになってしまいます。
配慮は心遣いであり、その場・その状況・相手の気持ちによって変化してくるものであると思います。
だから、武士道精神を磨くということは、他者の行動行為に対して指摘をしたり批判をすることではなく、自分の内面を見つめ、反省し、また自分を褒め、信念を持って生きることではないでしょうか。
これらを実践するために工夫をして、努力をすることは、艱難辛苦にも打ち勝つ力がつくことと思います。
力が付けば、嫌なことに遭遇しても辛い期間が短くて済みます。
まず、武士道で生きるため、使う言葉は肯定的な言葉にかえましょう。
否定的な言い回しを使っていると、どうしても不幸を呼び寄せてしまいます。
辛いな・・・ ⇒ 後一歩努力が必要なんだ
嫌になった・・・⇒ ちょっと飽きてきたから工夫をしてみよう
失礼な!!⇒ 面白い事をする人だ
などと言葉を変えるだけで、かなり不快さがなくなり、気分が晴れやかになります。
明るく楽しく生きていると、不思議と不幸は飛んでいってしまいます。
まるで、トトロの真っ黒クロスケがサツキとメイの家を出て行ったように。
競争
2010年5月17日

武士道ワンポイントレッスン
二回目のテーマは「競争」
競争をするのは悪いことなんでしょうか?
きっと競争の正しい意味を勘違いして覚えてしまった先生がいたのでしょうね。
だから、徒競走を全員で手をつないでゴールインなんておかしな事を思いついてしまったのでしょう。
物事悪い面だけを強調すると、真意をつかめないで失敗してしまいます。
良い面にもスポットライトを当てて、考えてみることが大切ですよね。
競争とは、
『同じ目標に向かって、同じ目的意識を持って、少しでも早く、少しでも良く、少しでも役に立つように、競い合うこと』
なんですから、世の中の発展のために良いことなんです。
人間は自分が世の中の役に立っていると自覚できたら、絶対自殺なんかしません。
自分が世の中にとって不要な存在だと思うから、自殺したくなるんですよ。
競争をしている時は確かに苦しいです。
でも競争を終えたとき、或いは途中で一息入れたとき、それが結果的に負けたとしても、大きく成長している自分を見出すことができるはずです。
今回のオリンピックのフィギュアスケートで真央ちゃんとキムヨナさんの戦いがありました。
私は負けた真央ちゃんの方が、将来を考えたら大きく成長したと思っています。
キムヨナさんのように、審査員の目を計算に入れて、オリンピックに勝つ事を目標としていたのと、真央ちゃんのようにヤグディンさんに憧れて曲を選び、自己ベストを目標としていたのと、どちらが自己成長になったのか? と考えたら、それは胸を張って真央ちゃんと私は言えると思います。
結果はもちろん審査員受けを狙った方が勝つのが当たり前と言えば当たり前でしょう。
また、競争によって技術が高まるのも確かだけど、それ以上に大切で貴重な成果は『心が強くなること、許容量が増すこと』です。
精神力が高まれば、逆境に遭遇してもあまり不幸と感じなくなり、全てを学びとして受け入れることができるようになります。
競争をすることから逃げる人ほど、競争心が強いともいえます。
負けるのが嫌だから、最初から競争をしないという選択をしているのです。
逃げてしまったら、成長するチャンスも逃してしまいます。
もったいないですよぉ~
競争を楽しんで、負けてもプライドなんか気にしないで、、学びになったことを喜びましょう。
プライドは人目です。人目を気にしていると自分の心をないがしろにしてしまいます。
人目より将来的な自己成長に目を向けましょう。
そして、勝つためにはどうしたら良いのかを、もっともっと真剣に、事前に工夫をして、必死に考えて取り組んでみましょう。
最初から負けてもいいや・・・なんて捨て鉢な気分で競争をしても、なんのプラスにもなりません。
精神的に強くなるわけでもなく、負けた汚名だけが残っているのに、自分の独りよがりで『最初から勝とうと思ってなかったんだよ』なんて負け惜しみを言ってもカッコ悪いってことを理解しておきましょうね。
競争することで社会を良くすることができるんだから、負けても世の中の役に立っているんです。
たとえば、少しでも良い商品を、安価で、提供するために、パナソニックとソニーと日立と・・・競争してくれているから、私たち便利に安く良い電化製品を使わせて頂いているではないですか。
今から意識を変えて、社会貢献をするために得意な分野で競争して、絶対勝とうと挑んで、負けても自分を褒めることができるくらいに真剣に取り組んでいきましょう。
By 本多百代・人間力向上セミナーより
2010年5月17日 10:16 PM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |
日本食~日本人の生き方
今日はお寿司を食べに連れて行っていただきました。
日本食はいいですね。
素のままの良さを上手に引き立たせています。
相手をねじ伏せて変えてしまうということをしない生き方なんですね。
お寿司のネタも魚を切るだけで、ムニエルにもしていないし、ミンチもしていない。
(ネギトロは別ですが・・・笑)
日本人の生き方は世界に誇れると思います。
そして、昨日はウズべキスタンから京都大学大学院博士課程に留学している
アブドゥラシィティ アブドゥラティフさんにお会いしました。
頭脳明晰でお話のセンスも素敵で、日本語が大変上手です。
私は最初日本人だと思って話していました。
武士道を外国人が学んでくださり世界中で武士道を実践したら
きっと、地球人の心は一つになるけれど、文化や歴史という個を大切にしあった
素晴らしい平和で戦争のない世界になると思います。
アブさん、地球人の心を一つに、それぞれの文化・文明を大切に、
国を越えて一緒に協力して叶えていきましょうね。よろしくお願いします。
2010年5月17日 10:02 PM | 日記 |
京都にて関西特賛委員会とお経の講義
2010年5月16日
京都より。
昨日と同じ事を京都会場でしました。
関西特賛委員会では、高垣さんが委員長、桜井さんご夫妻が副委員長、岡本さんが副委員長に就任頂きました。
中島さん、藤原さん、平井さん、加藤さん、高垣さんの奥さま、桜井さんの6歳のご子息ちゃまがご参加くださいました。
桜井さんのお子様は6歳で教育勅語を全て暗記していえるんです。
それに、3時間のお経の講座を大人と一緒に聞けて、その上会議まで参加して自己紹介もしたんです。
素晴らしいですね。みんなびっくり感動して涙も流して大人が拍手をおくっていました。
素敵な1日になりました。
2010年5月16日 11:53 PM | 日記 |