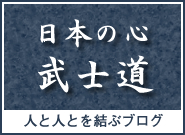合わない人と和を保つ方法
2010年9月9日

武士道ワンポイントレッスン
22回目のテーマは「合わない人と和を保つ方法」
自分の意見を持つことは大切です。自分と意見の合う人は良い人に感じます。でも、意見の合わない人はうっとうしい人になります。だから、「あの人いい人ね」という褒め言葉は、実際には「あの人は、私にとって都合の良い人なのよ」という意味の場合が多いですね。
逆に合わない人は、自分にとって都合が悪いことをする人だったり、褒め言葉を言ってくれずに注意ばかりしている人だったりすることがほとんどです。細かくてうるさいと思う人は、自分にゆとりがなくてそっとしておいてほしい時に特に感じたりしませんか。
しかし、この意見の合わない人から学ぶことは大変大きいものです。
意見の合う人とは何かを一緒に組んで進めるには適していますが、悪くなったときは補い合うこともできないという欠点があります。確かに好きなものが同じなら意見が合います。
だから食事に行くときや、遊びに行くときは楽しいでしょうが、食事でも残してはいけないところに行ったとき、または、全部種類の違うお弁当があって好きなものを取っていいと言われた時などは、好きなものが違う方が便利ですし、都合がよいではないですか。ましてや人間の好みだったら、好きな異性が同じになり奪い合いになることだってあり得ます。趣味が違えば奪い合いなどあり得るわけがない。
このように違う意見を受け入れるからこそ、丸い輪になり分け合いが自然にできるのであって、意見の違うものを排除していては雲丹みたいになってしまうし、最終的には喧嘩になってしまいます。
気の合わない人を受け入れるには、
①世の中、自分と同じ人は二人といない
②親の注意はイライラ腹立たしかったということを思い出す
③生きてきた環境が違えば判断が違って当然
この3つを頭に入れます。そうすると、嫌なことを言う人は、自分にとって為になることをしてくれていると思えてきます。
もちろん、その相手は意地悪をしているかもしれません。でも、受け取る自分が意地悪ととらなければ、いくら意地悪をされても、それは意地悪ではなくなるのです。意地悪ではなく、
①違うやり方を探すように仕向けてくれていると思う
②忍耐力をつけて、想像力と思考力をつけるチャンスを与えてくれている
③同じ異性やほしい物を奪い合わなくても済む
と思うことで、感謝する存在にすらなるわけです。
全てが旨くいくとは言えませんが、このような捉え方をしていたら、あまり悪い方向には傾いてしまういことはないでしょう。つまり、意地悪をしたりイジメをする人は、苛めたことで相手がダメージを受ける姿をみてストレス解消させています。
そうすると、苛めてもいつも明るく楽しそうにしていることが、一番良いしっぺ返しになるのではないでしょうか。しっぺ返しはしない方が良いと思いますが、でもそう思うことで救われた気持ちになることも確かです。つまり、自分の考え方、とらえ方、受け取り方次第で、いくらでも不愉快になるし、いくらでも幸せになるということです。
幸せになりたければ、自分の考え方やとらえ方を変えるしか方法はないのです。
合わない人と合わせなければならない職場などでは、自分の取り方次第、考え方次第だと思って、自分をコントロールする術を見つけましょう。和を保つとは、己の感情の調整能力を高めることなのです。
きっと心が乱されない素晴らしい毎日を送ることができるでしょう。
2010年9月9日 03:41 AM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |
ブルーな気分
2010年9月8日

今日は嵐ですね。
ジャニーズではありません。暴風雨の方です。
私は、パンを切っていて、久しぶりに指まで切ってしまいました。
まっすぐの刃の形をした包丁ではなく、ヒラヒラした刃の包丁だったから、ちょっとエグイきれ方をして・・・
たったこれだけで、けっこうブルーな気分になるものなのですね。
生体のエネルギー値は、髪の毛を切ってもダウンするとか。
仕方ないことなのかもしれない。
でも、武士道がまだまだしみわたっていない自分を発見。
まだまだ修行がたりないですね。
2010年9月8日 11:25 PM | 日記 |
母のお誕生日
2010年9月7日

今日は母のお誕生日です。
去年までは、「おめでとう」と言えたのに、今年からは母はこの世では年を重ねなくなりました。
親孝行ってやれそうでいて、なかなかできないものですね。
戦後の核家族化はより一層親孝行をすることが難しくなってしまったように思います。
一緒に住んでいないとできない親孝行がたくさんあります。
核家族は日本社会の礎である縦の絆を切ってしまったように思えてなりません。
親孝行したいときに親はなし・・・良く言ったものですね。
2010年9月7日 11:21 PM | 日記 |
今日はとてもうれしい一日でした
2010年9月5日

9月5日の日記
今日はとてもうれしい一日でした。
武士道協会人間力向上セミナーを東京で開き、前回の京都と同じように「子ども手当」について話し合いました。
ホワイトボードを各班に一台ずつ使い、和気あいあいに楽しく発表会。
若い年代の方の参加がだんだん増えてきて、やっと交流ができるようになりました。
今日はスポーツマンや、博学で紳士の男性も初参加。
初めてお会いしたのに意気投合。
帰りにオッティーに誘っていただき、誠実で穏やかな川名さん、指南役の鎌田さんと4人でランチを頂きました。
関東がだんだん関西と同じように活気が出てきたことに、今日は最高に幸せ気分。
あまり投稿のないこのブログ、きっと誰も見てないのでは…なんて思うこともあるのですが、今日は会ったとたんにオッティーからブログ見ましたと言われて、すごく嬉しかったです。
ハーモニーさんに苦労を掛けている甲斐がありました。
オッティー、ぜひ昼間に話していた夢を一緒に実現させましょう。
日本の未来のために!!
2010年9月5日 11:14 PM | 日記 |
たまには息抜きも良いものだ
2010年9月1日

9月1日の日記
東京近郊の温泉に行ってきました。
プライベートで遊びの時間を持つのは本当に久しぶりです。
最近は疲れがたまっていて、なかなか6時間以上の熟睡はできなかったのですが
翌朝気が付いたら8時になっているのでびっくりしました。
最初に岩盤浴に入り、51度の塩の岩盤浴から11度の氷の岩盤浴を行ったり来たり。
引き締まったつもりになって、露天風呂に行きました。
珍しい炭酸湯で、体の中にしみこんでいく感覚がありました。
露天風呂では壺湯、かけ流しの湯など入りました。極楽極楽!!
たまには息抜きも良いものだと思いました。
今は武士道協会にとっても正念場です。
今の努力が今後を左右するので、のんびり構えていられないので、ついつい忙しくし
ていることで安心していたように思います。
人間は、自分を追い込んでいるときって、精神的にゆとりを持つことに罪悪感を持つ
ように思います。
でも、その時にこそゆとりを持つことが大切なんですね。
「ゆとり」と「ゆるみ」をごっちゃにしていてはだめでした。
連れて行ってくれた人たちに感謝です。
2010年9月1日 09:25 PM | 日記 |
変化する日本の絆「家と個」
2010年8月28日

8月27日 日記
久しぶりに10代の時からの仲間に会ってきました。
その仲間のお兄様がバイクの事故で即死したそうです。
ずっと会っていない人なのに、ショックでした。
若い時の仲間だから、家族構成まですべてを知っているので、お母様の心中を察すると余りあることで、胸が苦しくなりました。
本当に人の命とは何と儚いものかと思わずにいられれませんでした。
会社を設立して、大きくしている最中だったそうです。
奥様(といっても私もよく知っていた方です)の居住地の近くに改めてお墓を買って入れたとのことで、長男だけど親(父親が既に他界)のお墓に入れなかったそうです。
理由は、死んでも近くにいてほしいからということでした。
お母様は息子の他界と自分の家のお墓に息子を入れてもらえなかったことの両方でショックだったようです。
それぞれの視点で考えると、どちらの気持ちもよくわかります。
でも、これで良かったのかしら? と他人事ながら考えさせられた事柄でした。
家という考えから、個という考え方に変化してきている証ではないかと思ったからです。
日本を支えてきた縦社会の絆が薄れつつあることを感じました。
やはり、息子、ましてや養子に出したわけでもない長男が、自分のお墓に入ってくれないことを生前に知る、一生懸命生んで育てた母親の気持ち。
子供が親より先に他界する親不孝(致し方ないことだけど一番の親不孝ですよね)に重なったことに、私までが重く感じてしましました。
また夫に突然先立たれた奥様の気持ちもとてもよくわかるのです。
でも、家族単位で生きてきた日本の風土があることも忘れてはならないと思いました。
たった65年でここまで変われるものか・・・とマッカーサー元帥の取った策の先見性にただ感服しています。
でもこれでは、我々の子供の代まで日本が持たないかもしれません。
世の中のあり方自体を考え直し、建て直さないと大変なことになると思った出来事でした。
2010年8月28日 11:45 PM | 日記 |
「人間力向上セミナー」(東京)のお知らせ
2010年8月26日
楽しく、幸せに、毎日を送れたらどんなにいいだろうとだれもが思うはずです。
しかし、逆境は誰にでも不意打ちで訪れます。
そんな時、冷静に、苦しまずに、解決策を見つける能力を身につけられたら、
どんなに楽で、自殺者などいなくなるだろう・・・と思うはずです。
“武士道の精神”が身についていれば、それは難なく可能なのです。
武士道協会主催 人間力向上セミナーは、現在起きている問題を考え
あるべき姿を話し合い、そして、提言していきます。
2010年9月5日(日)10時から3時間程度
2010年9月26日(日)10時から3時間程度
場所 PHP総合研究所東京 (半蔵門線半蔵門駅直結真上)
料金 会員無料 非会員一人1,000円
対象 18歳以上
講師 本多 百代
お申込みは武士道協会ホームページの
お問い合わせフォームからの入力↓
http://www.bushido.or.jp/contact.html
あるいは同フォームをプリントし、必要事項を記入した用紙をFAXでお願いします。
FAX: 075(681)3565
お問い合わせ: (090)681-5514
e‐mail: info@bushido.or.jp
担当 西尾 晴夫
人間力向上セミナーのチラシは下のアドレスから↓
https://sites.google.com/site/sinboas/ningenryoku_t100905
2010年8月26日 04:18 PM | NPO法人 武士道協会,日記 |
あなたのコメントが日本を変える!
2010年8月24日

いつもこのブログをご覧頂き、ありがとうございます。当ブログは、どの記事に対しましても、コメントが頂戴できる形になっておりますが、より一層皆様との交流をはかるべく、新コーナーを作りました。
特定の記事とは関係なくお書きになりたい場合は、本コーナーのコメントとしてお書き下さい。その場合はカギ括弧でタイトルをつけて頂ければ最高です。
(タイトル例:『私の武士道』)
コメント欄が用意されていない場合は、
その記事の一番下の「Coment(0)」をクリックすると、書き込み欄が出るようになっております。
コメントこそが、本多百代のエネルギー源です。皆様のお声を頂戴できれば、幸いでございます。よろしく、お願いいたします。 (管理者敬白)
「はかなさ」と「せつなさ」
2010年8月19日

武士道ワンポイントレッスン
21回目のテーマは「はかなさ」と「せつなさ」
人間は「はかなさを知る」ことが、無駄な焦りや競争心を起こさずに済むように思います。
「はかなさ」「せつなさ」とは、どんなに努力をしてもいかんともしがたいことがある事を知ることではないでしょうか。
生老病死がまさにそれです。
他には、愛する人から愛されない、背が高くなるように願っても遺伝でどうしようもない
このように、人生にはどうしようもないことがたくさんあるということなのです。
しかし、最も適した使い方は、「辛いことが多くて一生懸命乗り越えて生きているけど、必ず死んでしまったら何もあの世にはもっていけない」
と思った時この気持ちになるはずです。
「あの人が困っているから助けてあげたいのに、その力がない」という時でしょう。
特に我が子が病気で苦しんでいるのを見ている親や祖父母は、この気持ちで一杯になるはずです。
はかなさを知るとは、いくら努力して完成させても流れの中で生きている我々には、それをとどめ置く力がない、それでも努力を続ける必要がある事を理解することだと思います。
そうすれば、先を考えたら何もしたくなくなってしまったという事はなくなるはずです。
切なさを知るとは身を切られるような思いであるのに、何もすることができない、ただ祈るしかできず、悲しみを堪えなければならない。
己のふがいなさを責めたくなるような気持ちを味わい耐えることです。
諦めの境地になる人、自暴自棄になる人、凛として堪え出来る事をして気持ちの整理をする人、様々な対応の仕方があります。
どんなに辛くても、切なくても、努力をし続けていかなければならない、そういう宿命の元に命を授かっているのが我々人間なのです。
動物はここまで考えられないはずですし、はかなさを知らずに、目の前のことにのみに気持ち動くようです。
はかなさと切なさを感じたり知ったりできるということは、人間である証であり、考える力があるからです。
はかなさを知って、開き直ってしまい「どうせ死ぬんだから、生きている間に好きな事をしておかなきゃ損だ」と考えたとします。
きっと、遊び三昧でしょう。
しかし、「一度しかない人生を、悔いを残さないように、後に残る子孫が恥ずかしい思いをしないように生きよう」と思ったとします。
きっと、世のため人のために良い事を一生懸命考えて行動に移していくことでしょう。
どちらが得か? 正直申し上げますと、死んで見なければ解らないでしょう。
でも、死後の世界があったとしたら、後者の生き方をした方が後悔しないでしょう。
また、死後の世界がなかったら、良いも悪いも解らなくなってしまうのですから、どっちも同じではないですか。
そうなら、子々孫々末裔まで誇れる人物でいた方が、生きている人の中で生き続けるイメージは良くなります。
一点のみで判断せず、多角面での判断をすることが、楽に生きる術に思います。
2010年8月19日 03:43 AM | 日記,武士道ワンポイントレッスン |
猛暑の中、天満社で
2010年8月18日

8月18日の日記
私がいる部屋の窓から、いつも天満社の杜が見えています。
廊下側の窓からは教会の十字架が見えています。
神様に囲まれた凄い環境です。
今まであまり気になっていなかったのですが、今日は猛暑の中、どうしても天満社にいきたくなり、急遽参拝に出かけてきました。
急な長い階段を登り、途中の広場のようなところに出てから、もう一度階段を登るとお社に着きます。
階段を登る時は、わき目もふらず、ただ足元だけを見て、息を大きく吸いながら登りつめました。
そうでないと苦しくなってしまうほど、運動不足状態だからです。
木々で囲まれていて、景色が見渡せるというわけではありません。
神社の下には川が流れ、それに平行して名鉄本線が走っています。
お参りを済ませ、長い階段を降り始めて少ししたら、足がガクッとしました。
うっそぉーーー!!
つっかけサンダルを履いていったのですが、ベルトの脇がバキッとはがれてしまっていました。
鼻緒が切れたのと同じで何か悪い知らせ???
と思うと同時に「どうしよう!!歩けない」
どうにもこうにも、びっこを引くことすらできません。
はだしで歩くか、片足ケンケンしてかえるしか方法がない!!
でも帰りは緩やかな坂道を10分ほど登らなければならないのです。
この炎天下に裸足ではアスファルトの路面が熱くて歩けないし、片足ケンケンは心臓が破裂しそう・・・
しばし呆然としてから、安全ピンなどこの袋に入っているわけないわ・・・と思いながらも小さな布の手提げの中を見ました。
お財布とタオルハンカチと携帯しかない・・・・役に立たないものばかり。
出てくるときに、お賽銭のためにお財布と汗を拭くために小さいフリフリのついたハンカチにしようと思った時、暑くて汗をかきそうだから大きい方にしようと思って大きめのハンドタオルにしたのです。
それが功を奏しました。
これだ!! タオルハンカチを三角に折って、サンダルの底から足の甲までを一緒に結びました。
大き目のハンドタオルにして良かった。
歩けるではないですか!! やったぁ~!!
安心して嬉しくなりました。
その瞬間、鼻緒が切れるのって不吉な予感? と思い出しました。
心配になって父に電話をして「元気?大丈夫?」と聞いて、ここは大丈夫。
それから、ゆっくりゆっくり帰りました。
無事到着してからサンダルとハンカチを処分してから、鼻緒が切れた事はどういうことか調べました。
そうしたら、昔、死人を埋葬する時に、お墓の土を踏んだ草履は死の穢れがつくと思われていたそうです。
そこで、お墓の入り口で脱ぎ捨てて帰る慣わしだったとのことです。
そのとき、その草履を死霊さんや妖怪がはいてついて来れないように鼻緒を切って捨ててきたそうです。
だから、突然鼻緒が切れるのは不吉な知らせと思われたようです。
だから、厄落としになると書いてありました。
なんかホッとしました。
そうか、工夫をすれば難を逃れられるということだったんだ、と妙に納得して気分がよくなりました。
天満社の神様、ありがとうございました。
お蔭様です。
2010年8月18日 11:37 PM | 日記 |