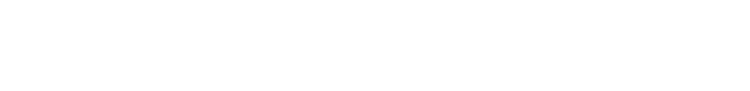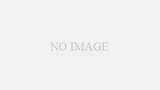第1回シン武士道懇話会
テーマ:「武士道は自己陶冶に精励する」講演者:青山 誠
開催日時:令和7年9月28日(午後3時~午後5時)
武士道は自己陶冶に精励する
【1. 『猛省録』とは何か】
・著者:吉田松陰(1830–1859) ・執筆時期:安政5年(1858年)6月頃
下田踏海事件による再収監。謹慎から正式な獄入りへ移行(松陰23歳)
■補説:『猛省録』の教育的意義と現代的活用
・『猛省録』は「自己を省みることから始まる学び」の象徴。
・単なる読書ノートではなく、志を古人の事績に照らして確認し、日々の行動に活かすための実践録。
・読む→書く→行う→また書く、という記録の方法は塾生にも応用可能。
・古人の事績を記録し、自らの志と照らし合わせることで、学びが抽象的知識から具体的行動へと転化する。
・松陰の「初一念」の深さと実践性を伝えることで、「自分は何に猛省すべきか」「何を志としているか」を問い直す契機となる。
【2. 松陰の思想的背景】
・陽明学の影響:王陽明『伝習録』に学び、「知行合一」の思想を実践に昇華。
・国体認識の形成:会沢正志斎『新論』を通じて、国体と世界認識を志の中核に据える。
・志の数値化と行動化:『二十一回猛士の説』にて、志を数値で表し、猛き行動として自らに課す。
・誠の実践と逆境の学び:『三余説』『睡余事録』に記されたように、獄中でも学びを止めず、誠を尽くして筆を執り続けた。
・教育理念の明示:『松下村塾記』に「学は人たる所以を学ぶなり」と記し、身分を超えた共学の場を築く。
【3. 国事と死生観】
・ペリー来航(嘉永6年・1853年)に即応し、国体の危機を憂う。
・下田踏海(嘉永7年・1854年):武力ではなく「知的越境」による国防を志す。
・『留魂録』:処刑直前に記した遺書。志を死後に遺す覚悟。
・辞世の句: 「親思う 心にまさる 親心 今日のおとずれ 何ときくらん」
→ 親心への感謝と、至誠の極みを示す。
【4. 『猛省録』登場人物一覧】(すべて中国の古人)
蘇洵(そじゅん) 北宋の文人。「兀然端座」の姿勢に学び、蟄居中の自己鍛錬の象徴。
胡踠瑗(こえんえん) 北宋時代の儒者。朱子学の先駆者。
多斯達篤(たし・たっとく) 清代の人物。廉潔・誠実の象徴として引用される。
王安石(おう・あんせき) 北宋の政治家・思想家。「性情は共に心にある一の存在で、同質のものであるが、それが内にありて動かざる時は、性であり、外に発して情となるにすぎない」
陽城(よう・じょう) 唐代の清廉な官吏。私利を排した姿勢に松陰が共鳴。
司馬光(しば・こう) 宋代の政治家・歴史家。誠実・慎重な政治姿勢に学ぶ。
何渉(か・しょう) 後漢の儒者。剛直・廉潔の精神を象徴。
范仲淹(はん・ちゅうえん) 北宋の政治家・文人。また明治天皇の愛読書だった『宋名臣現行録』でも紹介された「先憂後楽」の思想に深く共鳴。
韓愈(かん・ゆ) 唐代の文人・儒学者。文道一致の思想に学び、文章と道徳の融合を志向。
【4. 結語】
松陰の自己陶冶は、志に始まり、誠に貫かれ、学によって深まり、国への思いによって広がり、死生を超えて未来へと継がれていく。 彼の語録は今も私たちに問いかけ続けている――
「あなたは、何のために学び、何を遺そうとしているのか」
第二章
柳生宗矩に見る自己陶冶の思想 ―兵法を以て心を磨き、職分を覚る道―
【1. 人物概要】
・柳生但馬守宗矩(1571–1646) ・徳川家康・秀忠・家光の三代に仕え、将軍家御流儀の確立に深く関与。
・柳生新陰流の理論体系の構築にも寄与した剣士。
・兵法を「心を磨き、職分を覚る道」として捉えていたと考えられる。
【2. 主著『兵法家伝書』と兵法の位置づけ】
・三巻構成:「進履橋」「殺人刀」「活人剣」 ・技法と心法の両面を体系的に記した伝書。
・兵法は「人を斬る技」ではなく、「己を律し、他者を導く道」として展開された。
【3. 自己陶冶を照らす言葉群】
・「兵法は、心を磨く鏡なり。鏡曇らば、敵を見誤る」
→ 外敵に勝つより、内なる欲・怒り・慢心に克つ修行。
・「われ人に勝つ道は知らず、われに勝つ道を知りたり」 → 自己に克つことこそ兵法の本質。
・「道者の胸の内は、鏡のごとくにして…是只、平常心也」 → 無心・平常心の境地を重視。
・「平常心を以て、一切の事をなす人、是を名人と云う也」 → 技と心の一致を目指す修養。
・「習いを忘れ、心を捨てきって…道の至極也」 → 無心の境地こそが道の極み。
・「道とは、何たる事を云うぞと問へば、常の心を道と云う也」 → 特別な心ではなく、平常心こそが道。
・「道ある人は、本心に基づきて、妄心を薄くするゆえに、尊し」 → 誠実な心が技術を支える。
・「妄心は何事をなせども、邪也…兵法も負へし」 → 私欲や偏見が兵法を損なう。
【4. 三層構造による兵法思想の展開】
技の層:剣術の習得を通じて身体と心を整える
心の層:禅的心法により無心・平常心を養う
志の層:剣をもって人を導き、世を治める器を育む → 技術の向上ではなく、人格形成と職分の覚悟へと至る
【5. 死生観と自然の理】
・「人の死するは、有かくるゝ也。人の生るゝは、無あらはるゝなり。其躰常なる者也」
→ 死と生を一如として捉える禅的境地 → 死を飾らず、自然の理として受け入れる姿勢
【6. 結語:一心に収める教訓】
・「一心、多事に渉り、多事、一心に収まる」
→ 複雑な事象を一つの心で受け止め、また一つの心に還元する教訓
・宗矩の兵法は、技と心を一体化し、誠をもって治国に資する武士道の深化
・「心を磨き、職分を覚る道」は、誠殿が目指す「天地自然の理法と共に生きる」思想と深く響き合う
宮本武蔵に見る自己陶冶の思想―『五輪書』に見る求道の精神―
【1. 人物概要】
・宮本武蔵(1584–1645)
・「二天一流」創始者。生涯無敗の剣士として知られる。
・晩年に『五輪書』を著し、兵法を通じた求道の精神を展開。
・播磨国出身。十三歳で初勝利、二十八歳までに六十余度の勝負にすべて勝利。
・三十代以降は勝敗を超え、天理と兵法の本質を探究。
【2. 『五輪書』の構成と執筆姿勢】
・五巻構成:地・水・火・風・空 ・仏法・儒道・軍記に頼らず、自らの見立てと真実の心を記す。
・「天道と観世音を鏡とし、寅の刻に筆を執る」──求道の姿勢が序文に表れる。
【3. 命を賭して鍛える兵法の精粋(火の巻より)】
・兵法は命がけの修行であり、実戦でしか得られない体得がある。
・「些細な理屈や弱い発想は、命のやり取りの場では無意味」
・「十人に勝つ者が千人に勝ち、万人に勝つ」──兵法の原理は数に左右されない。
・一人で太刀を取り、万人に勝つ境地を目指す孤高の修行。
・修行を極めた者には、自然と自由が生まれ、神通力のような効験が現れる。
【4. 形なき道を悟る「空の巻」の思想】
・空とは、形なき真理であり、迷いを離れた心の境地。
・「有るを知り、無きも知る」ことで到達する。
・偏見やひいきを離れ、直道と真実の心をもって兵法を行うことが空の実践。
・「空を道とし、道を空と見る」──精神の自由と自己超越の象徴。
■整理された思想ポイント
・空は迷いを離れた心の境地 ・武士としての道を修め、心と眼を磨くことで見えてくる
・偏見を離れ、真実の心で兵法を行うことが空の実践
・「善ありて悪なし」「智・理・道は有なり」「心は空なり」──精神の成熟を示す
【5. 結語】
・武蔵の兵法は、勝敗を超え、誠を尽くして己を磨く求道の道。
・「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とす」──日々の鍛錬による道の深化。
・武蔵は兵法を通じて「生き方そのもの」を鍛え抜いた人物。
・その思想は、「理念と実務の統合」「精神の成熟」「天地自然の理法と共に生きる」ことと深く響き合う。
山岡鉄舟に見る自己陶冶の思想―剣・禅・書を貫く誠の修行―
【1. 人物概要】
・山岡鉄舟(1836–1888)
・剣術家・禅者・書家。「幕末の三舟」の一人。
・江戸無血開城の立役者。明治天皇の侍従として10年仕える。
・「至誠一貫」を信条とし、名利を超えて職分を果たす姿勢を貫いた。
【2. 剣の道:無刀流と誓願の修行】
・幼少期から神陰流・北辰一刀流・槍術などを修める。
・浅利義明に敗北後、弟子入りし「無刀流」を創始。
・「無刀流」=心の統一と洞察によって勝つ境地。
・誓願三期:
第一期:1000日稽古+200回立ち切り試合
第二期:3日間で600回
第三期:7日間で1400回(鉄舟自身が達成)
・誓願は技術の試練ではなく、誠を貫く自己陶冶の儀式。
【3. 禅の道:剣禅一致と悟りの体験】
・滴水和尚より「両刃交鋒」の公案を授かる。
・三年間、昼は剣術・夜は禅に没頭。
・深い三昧の後、門人・師匠との試合で「無敵の境地」に至る。
・「三界唯一心也…妙応無方、朕跡を留めず」 → 剣が慈悲の剣へと昇華された瞬間。
【4. 書の道:無心の書と人格の表現】
・15歳で弘法大師流入木道52世を継ぎ「一楽斎」と号す。
・「書は人なり」──型に囚われず、心のままに筆を走らせる。
・書を通じて自己の心を映し出す修養の場とした。
【6. 実践と死生観】
・江戸無血開城:命を懸けて誠を尽くす交渉。
・功績を誇らず、勲三等を辞退し、勝海舟に手柄を譲る。
・最期は皇居に向かって結跏趺坐のまま絶命。
・門人の中には殉死を試みる者もいたと伝えられる。
【7. 現代への継承】
・東京都港区白金台「スパ白金」にて七代目井﨑武廣師範が指導。
・形稽古・竹刀稽古・巻藁立ち切りなど、鉄舟の思想を身体で実践。